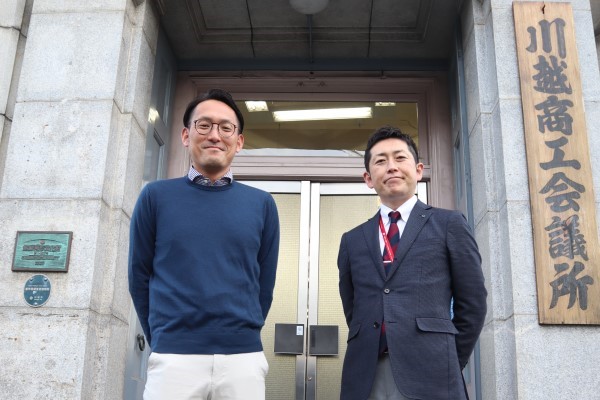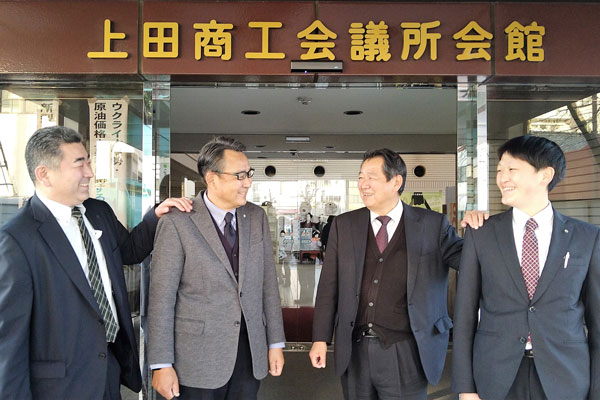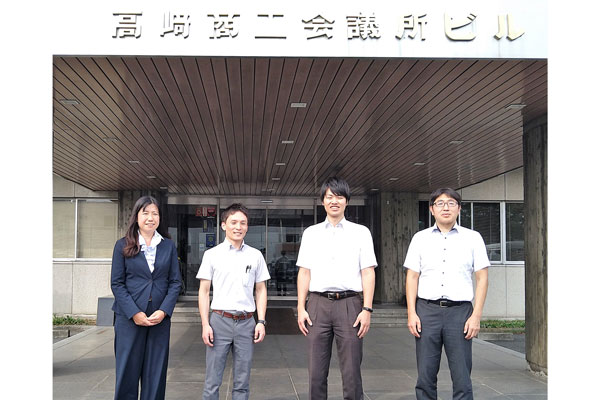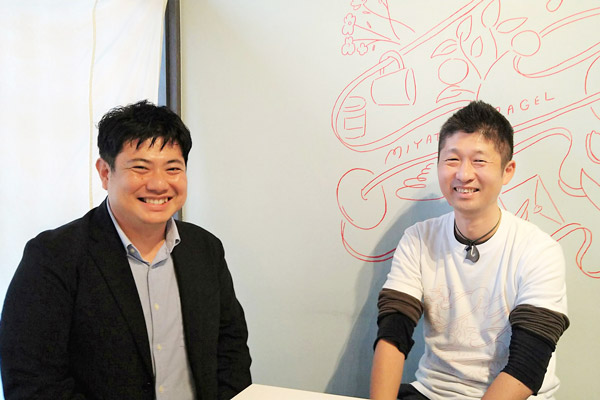経営支援の現場から
よろず支援拠点と連携、地元の企業に手厚い経営支援が可能に:斜里町商工会(北海道斜里町)
2025年 11月 10日

北海道斜里町は世界自然遺産・知床の玄関口として知られる。コロナ禍で低迷していた観光需要がじわじわと回復しており、経済的にも大きなポテンシャルを持った地域だ。約330の事業者が会員となっている斜里町商工会は地域の活性化に向けて、2018年から町内の事業者への積極的な経営支援に取り組んでいる。国の支援機関である「北海道よろず支援拠点」と緊密な協力関係を構築。専門家を招いた相談会の定期開催や事業者の伴走支援を実施するとともに、商工会の支援能力向上にもつなげている。
広大な北海道、きめ細かい事業者支援に課題

「事業者支援のために町が予算を組んで、よろず支援拠点を積極的に活用する事例は北海道だけでなく、全国的にもそう多くはない。地域を活性化させたいという町全体の思いを強く感じている」。こう語るのは、北海道よろず支援拠点のチーフコーディネーター、中野貴英氏。3カ月に2回のペースで町に赴き、斜里町商工会と連携し、出張経営相談会を開催している。
北海道よろず支援拠点は、全国47都道府県に設けられた「よろず支援拠点」の一つで、北海道中小企業総合支援センターが運営している。中小企業診断士や弁護士、税理士をはじめ、経営に関する専門的な知見を持ったコーディネーターが約30人所属し、道内の中小企業や小規模事業者が抱える経営に関するさまざまな相談に無料で対応している。
北海道で事業を営む事業者にきめ細かい支援を実施するため、北海道よろず支援拠点では、旭川や北見、釧路など道内6地域にサテライト拠点を設け、毎週1~2日程度、事業者の相談を受け付けている。ただ、北海道はあまりにも広大で、サテライト拠点での相談も周辺事業者への対応が中心になってしまっているのが実情だ。
北海道よろず支援拠点の本部がある札幌市から斜里町までの直線距離は約300キロ。東京から仙台、名古屋までの距離に相当する。最も近いサテライト拠点である北見市からも約60キロの距離がある。「他の地域でも出張相談会を毎月開催しているところはあるが、斜里町のように札幌から離れていると、そう頻繁に出張相談を開くのは難しい」と中野氏は語った。
経営者の実情に沿った適切な支援を目指す

そんな斜里町での定期的な出張相談を可能にしているのは、町によるサポートがしっかりしていることが背景にある。
斜里町では、商工会が事業者支援の重要な役割を担っているが、補助金に頼った支援が多く、踏み込んだ経営支援ができていないことが課題だった。「補助金の交付は手続きを踏めば、ある意味、簡単にできる。だが、それで果たして本当に有効に活用されているのか、補助金を交付するだけでいいのか。経営相談をして、しっかりと事業者の実情を把握し、必要なものに対して、必要な額を投じるような制度が必要なのではないか。そんな問題意識が町の中に生まれてきた」と斜里町商工会の指導課長で法定経営指導員の小野寺士(まもる)氏は語る。
そこで斜里町は2018年に町内の事業者に対する支援体制を強化するため、「知床しゃりビジネスサポート事業」をスタートさせた。町や商工会、金融機関、支援機関などが連携し、町内の中小企業・小規模事業者の支援にあたる取り組みだ。この事業を進める中で、北海道よろず支援拠点との協力関係が生まれていった。
北海道よろず支援拠点の出張相談を開催するのにあたっては、ビジネスサポート事業の予算でコーディネーターの飛行機代を拠出。専門家が出張しやすい環境を整備している。車や鉄道での移動よりも短時間で移動でき、事業者への対応により多くの時間を割けるようにした。
定期的に出張相談やセミナーを開催するようになると、これまで専門家に経営相談することにあまり慣れていなかった地域の事業者も積極的に相談会に参加するようになり、相談の内容も具体的になってきたという。中野氏によると、「飛行機の都合で、1回の出張で相談の対応ができるのは7件くらいだが、告知すると、ほぼ毎回、相談の枠が埋まってしまうほど盛況になっている」という。
伴走型の支援で第三者との事業承継サポート

一方、よろず支援拠点との協力関係を構築したことによって、町の事業者に対して、これまで以上に踏み込んだ経営支援にも取り組めるようになった。
斜里町の温泉宿泊施設の事業承継では、2024年から小野寺氏と中野氏が連携してサポート。新たな経営者に対しても伴走型の支援を実施している。
この宿泊温泉施設は、公衆浴場として昭和の時代から町民たちに利用されてきた。しかし、旧経営者が高齢となり、親族に後継者がいなかったことから、第三者による事業承継を模索していた。承継後も従来通り事業を継続することを条件としていたが、興味を示す事業者は「社員寮にしたい」「宿泊事業だけ続ける」といったものばかりで、旧経営者の条件に見合う承継先をみつけることができなかった。そこで、旧経営者は民間のマッチングサイトに登録。すると、条件に合う承継先が現れた。
マッチングの相手は東京に住んでいた元地方公務員。退職後、斜里町への移住を考えていたところ、サイトで温泉施設の事業譲渡の情報を見つけ、旧経営者に事業承継を申し出た。
旧経営者は商工会の会員で、マッチングが決まった話は小野寺氏のもとにも届いた。小野寺氏は「支援の必要性を強く感じた」と語った。小野寺氏が旧経営者に申し出て、支援が動き出した。
承継先の自己資金にも限りがあり、資金調達が課題だった。施設が老朽化していることもあり、金融機関は厳しい見方だったそうだ。借り入れができたとしても返済しなければならない。小野寺氏は中野氏に相談。連携して支援にあたることになった。
「こうした交渉事にはそれぞれの思いがある。金融機関は金融機関、事業者はいくらで譲渡し、継ぐ側はいくらで引き受けるか。そして、その後に事業を続けられるか。思い入れだけではまとまらないので、具体的な話をしていった」と中野氏。東京に住む承継先とはリモートでつなぎ、今後の対応を練った。
「複数の事業計画を作成し、資金調達を含め、事業承継に向けた今後のプランやスケジュールを作っていった。『こういう出方だと、こういうことをしよう』というアクションプランも考えた」と小野寺氏。半年ほどかけてそのプランを実践した。すると、金融機関から融資の申し出があり、大きな課題だった資金調達の問題をクリアすることができ、事業譲渡が実現した。
新規事業を計画、承継後の安定経営目指す

事業譲渡の決め手の一つとなったのが、宿泊温泉施設を活用した新規事業を提案したことだった。
小野寺氏と中野氏は、譲渡後の経営基盤の安定化策として、温泉宿泊施設の一角に地元で栽培された野菜などの農産物直売所を開設する計画を立てた。温泉宿泊施設はJR知床斜里駅から徒歩5分ほどの距離。町の中心市街地に近く、地元住民に加え、観光客による購買需要も期待できる。
斜里町は農業が盛んで、水産業とともに町の基幹産業となっている。しかし、町内には目立った農産物の産直売り場が設けられていなかった。小野寺氏によると、町の農家の多くは、小麦や、砂糖の原料となるてん菜、ジャガイモといった農産物を事業者向けに大規模に生産しており、消費者向けの野菜などを生産する農家が少ないことが背景にあるそうだ。

駅の近くには、土産物などを売る「道の駅」があるが、地元の新鮮な野菜などを売るスペースがなく、観光客から不満の声が寄せられていた。道の駅などにある産直コーナーは全国各地で観光の大きな目玉になっている。観光客だけでなく、地元の住民も買いに来ており、午前中に売り切れる直売所も少なくない。これまで町になかった農産物直売所を常設できれば、町の観光に新たな魅力を加えることができる。温泉施設の経営支援と町の観光振興のダブルの効果を狙ったアイデアだ。
計画の実現に向けては、北海道よろず支援拠点も積極的にサポート。農産物直売所などの支援で豊富な実績を持つコーディネーター、田所かおり氏にも加わってもらった。小野寺氏が消費者向けの農産物を販売する数少ない地元の農業事業者を訪問し、取り組みへの協力を依頼する際には、中野氏と田所氏、温泉施設の経営を引き継いだ新オーナーも同行。「斜里町のためにもなるのはいいこと。知り合いの農家にも声をかけたい」と、積極的な協力を取り付けた。

10月4日に開催した初のイベントには、農業を営む5事業者が参加。タマネギのつめ放題をはじめ、ジャガイモ、トマト、ナスなどの野菜が格安の価格で販売され、地元の住民が来店した。小野寺氏は「来年以降、販売する機会を増やしていきたい。そこから観光客も立ち寄ってくれるように常設の販売施設に結び付けていきたい」と期待を込めた。
新たな経営者による温泉宿泊施設の経営はまだ始まったばかり。町民たちの憩いの場をいかに守り、将来にわたって継続していくか。その大きなカギを握るチャレンジはこれから大きな本番を迎える。
商工会の経営指導者のスキルアップにも大きな効果

斜里町商工会と北海道よろず支援拠点との協力関係が生まれてから、2025年で7年ほどになる。連携の一環として、商工会はよろず支援拠点のコーディネーターを招いた研修を実施しており、小野寺氏ら経営指導員のスキルアップに大きな効果を上げている。
「7年間の蓄積の中でよろず支援拠点のどのコーディネーターを活用すれば、対応している事業者の課題解決にアプローチできるかよくわかっている。その意味で、よろず支援拠点の活用スキルはどこの地域よりも高い」と中野氏は小野寺氏を評価していた。
今回の農産物直売所の開設に向けた取り組みでも、小野寺氏が農産物直売所事業に詳しい田所氏を指名し、サポートに加わってもらった。「私自身が野菜の直売所のことは知らないので、コーディネーターにいろいろと質問して教えてもらう。それだけでは足りないので、自分は自分で勉強をして、知識を増やしたうえで分からないことを質問する。そうすることで、よりよいサポートをしてもらえると思っている」と小野寺氏は話していた。
北は北海道から南は沖縄まで全国1724の自治体のどこかに難しい経営課題を抱えた経営者がいる。適切な経営支援をすることで成長が期待できる中小企業・小規模事業者は数多く潜んでいる。こうした事業者を掘り起こすうえで、地域の商工会や商工会議所の役割は大きい。商工会単体では難しい支援も、北海道よろず支援拠点のような支援機関や金融機関、自治体などの連携・協力によってより強力な支援につなげ、また、地域の支援機関のスキルを向上させることができる。そのことを斜里町と北海道よろず支援拠点の取り組みが示している。
事例紹介
思い出の地への移住を決意 運転士からのチャレンジ 株式会社グリーン温泉(北海道斜里町、新沼隆代表取締役)

「仕事を早期退職して北海道への移住を考えていた。しかし、なかなかいい仕事がなくて踏み切れなかった。ところが、ある時、ネットを見ていたところ、この温泉が売りに出ていた。『あのグリーン温泉だ!』と、すぐに飛びついた」と、株式会社グリーン温泉の経営を引き継ぎ、新たな代表取締役になった新沼隆氏は、承継に踏み切った経緯を話す。2023年ごろのことだった。
東京都交通局に勤務し、地下鉄の運転士を務めていた新沼氏は、斜里町と浅からぬ縁を持っていた。マラソンが趣味の新沼氏は2003年にサロマ湖岸100キロを走破するマラソン大会にエントリーした。その時、斜里町商工会が開催したエクスカレーションツアーに参加。地元の人たちと仲良くなった。たまたま民宿でアルバイトをしていた妻と出会ったのもそのときだった。結婚して翌年開催されたマラソン大会に参加すると、斜里町の人たちがお祝いをしてくれた。その宴会が行われたのがグリーン温泉だった。
グリーン温泉の創業は1981年(昭和56年)。大正時代から続く呉服店の経営者が温泉を掘り、事業を始めた。植物性の有機物が豊富な天然モール温泉で、黒褐色の湯は美肌などの効果がある。一般の人たちも入れる公衆温浴施設とともに宿泊施設も運営。温浴施設には1日100人ほどが入浴に訪れ、夕方になると、駐車場に車が埋まるほど。40年以上にわたって地元の人たちに親しまれている。

「今日は誰も来ないな、と思っていると、お客さんが一人やってきて、そのあとに続々とほかのお客さんがやってくる。連絡を取っているのか、急に込んでくる。聞くと、みんなで背中を流し合っているそうだ」と新沼氏は話す。
宿泊施設は17室設けられている。工事関係者の利用が多く、「みな連泊で、長い人は1~2カ月泊まられる方もいる」と新沼氏は話す。観光客や新規顧客をターゲットにしたPRは一切せず、常連客とその口コミだけで安定して宿泊客を確保している。
旧経営者が事業の継続を承継の条件としたのは、長年にわたって利用してもらっている顧客を大切にしたいという思いからだった。新沼氏は旧経営者とやり取りをする中で、「お世話になった斜里の人たちに恩返しがしたい」という思いに駆られ、事業を引き継ぐ決意をした。

だが、経営の経験はなく、手持ちの資金もゼロに近かった。資金調達ができなければあきらめざるを得ない状況の中で、斜里商工会の小野寺氏や北海道よろず支援拠点の中野氏のサポートが入った。「わらにもすがる思いだったが、小野寺さんと中野さんが的確に方向性を示してくれて、資金の調達もでき、思いを実現してくれた」と新沼氏は感謝する。
3者で事業承継に向けた打ち合わせを進める中では「やめた方がいい」という説得も受けたそうだ。それでも意思を変えず、事業承継が実現した。
温泉宿泊施設としては安定した収入がある一方、金融機関からの借り入れの返済や老朽化した施設の改修が待ち構えている。農産物直売所の新規事業に取り組むのは新たな収益を確保し、将来訪れるであろう課題に対応することを目指している。
事業を引き継いだのは2025年6月。施設の運営や経理など旧経営者のサポートを受けながら経営を一から学ぶ。パートを雇いながら、自らも掃除やサウナタオルの洗濯など雑務をこなす。「憧れの斜里に住んでのんびり暮らしたいと思ったが、のんびりはできない。それでも以前の仕事に比べるとストレスは少ない」と笑顔をみせた。息子の学校の関係で妻とは離れた生活をしているが、妻も斜里生活を楽しみにしているそうだ。「事業を引き継いで、グリーン温泉を継続させたいというたくさんの人の思いを感じた。ぜひその思いを実現させていきたい」と、新沼氏は決意を新たにしている。