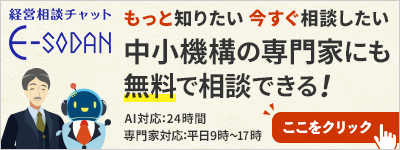あの人気商品はこうして開発された「飲料編」
「サントリーウイスキー角瓶」低迷するウイスキーを復権させた秘策


ハイボールが売れに売れている。2009年はサントリーのウイスキー「角瓶」が牽引役となり、ハイボール復権の年となった。まさに昭和30年代に人気だったウイスキーのハイボールが半世紀の星霜を経て戻ってきたのだ。そしてかつてのブームと同様に、現代の若者の心をとらえたハイボールはいまや社会現象になった。
その仕掛け人であるサントリー酒類(株)ウイスキー部・塚原大輔さんは語る。
「閉塞感が広がる日本社会において、現代の若者は、昔の元気だった時代にある種の憧れをもっています。そこにハイボールが登場し、若者の嗜好をとらえたといえます」
若者の琴線に触れたハイボール。それは半世紀前の元気な日本を彷彿とさせ、彼らの憧憬の的となった。そしてそれがハイボール復権の始まりだった。
今回のハイボール人気は、サントリーウイスキー角瓶をソーダで割ったいわゆる“角ハイボール”が先導した。まずはその角瓶の誕生秘話から始めよう。
国産ウイスキーづくりの夢を求めて
角瓶はつとに知られるよう日本の洋酒文化の原点ともいえる。発売はボトルのラベルに記されるよう1937年だ。この年、盧溝橋事件を機に日中戦争が勃発し、国内では角聖・双葉山が横綱に昇進、また石坂洋次郎の小説「若い人」や藤山一郎の唄う「青い背広で」がヒットするなど、その世相は高揚感につつまれていた。
そんな時代に生まれた角瓶はサントリーの救世主でもあった。というのも、角瓶を発売する直前のサントリーは、ウイスキー事業の不振でまさに経営が青息吐息、それを救ったのが角瓶だった。
ところで、サントリーはなぜ経営苦境に陥っていたのか。それは角瓶誕生の30年前に遡る。
1907年、サントリーの創業者・鳥井信治郎は「赤玉ポートワイン」を発売した。これが大ヒットして信治郎は大きな財をなし、21年にはサントリーの前身である寿屋を創業した。その時、信治郎には大きな夢があった。ウイスキーの国産化だ。というのも、当時のウイスキーは輸入ものしかなく、一部の上流階級しか飲めない高級なアルコール飲料だった。誰もが飲めるウイスキー、そして日本の風土に合った、日本人に愛されるウイスキーをつくり出す。それが信治郎の夢だった。
夢に向かって奮闘した結果、1929年に初の国産ウイスキー「サントリーウイスキー白札」(サントリーホワイトの前身)を発売したがさっぱり売れなかった。ビートの香りが強すぎたため、焦げくさく、煙くさいウイスキーに仕上がってしまったことが大きな原因だった。

そして翌年にウイスキーの「赤札」を発売するが、またしても不振に見舞われる。そのため資金繰りはひっ迫し、31年にはウイスキーの仕込みさえできない窮状に陥ってしまった。
夢を追い求めて国産ウイスキーづくりに邁進するものの、まさに悪戦苦闘の日々。倒産の瀬戸際まで追い込まれた信治郎は、37年に捲土重来を期して「角瓶」を発売した。ピート香が少なくしっかりとした味わい。繊細ながらも豊かな香り。まさにこの本格的な味が人々の嗜好をとらえた。
また、ボトルデザインは日本画家で寿屋のチーフデザイナーだった井上木它が薩摩切り子の亀甲紋をモチーフに考案。信治郎が「亀は万年。井上はん、ほんまにええ仕事をしてくれましたな。きっとこの瓶は万年も残りまっせ」と歓喜の声を挙げたよう、ソフィスティケートされた形状は現在もそのままに保たれる。
この洗練された味とデザインをもって誕生した角瓶は大ヒットとなり、倒産の危機にあったサントリー(当時の寿屋)を起死回生につなげる"救世主"となったのだ。
ウイスキーの復権を賭ける
時は下り、戦後の復興とその後の経済成長の時代になると、サントリーはリーズナブルなウイスキー「トリス」で一世を風靡する。ユーモラスなイメージキャラクターを用いた広告や専用酒場「トリスバー」が話題を呼び、ウイスキー人口が飛躍的に増えていった。そしてトリスバーでウイスキーの味になじんだサラリーマンたちは、所得が増えるにつれトリスや「レッド」から角瓶、「オールド」へとウイスキーのグレードを上げていった。そしてオールドが水割りという飲み方を人々に提供してそれが受け入れられた時、ウイスキーは黄金期を迎える。なんとピーク時のオールドの出荷は年間1200万ケース(12本/ケース)という空前絶後の実績を記録したのだ。


が、バブル景気を頂点にウイスキー需要はダウントレンドに入ってしまう。アルコール飲料が多様化するかたわら、かつての経済成長を支えた鯨飲派企業戦士の多くがつぎつぎに定年退職し、いわゆる盛り場風景、酒場事情が大きく変貌してしまったからだ。
「いまやウイスキーは50~60代の男の酒で、1人で飲むといったイメージです。それはそれでウイスキー特有の貴重な価値なのですが、もっと若い世代にも飲んでもらわないと、50~60代が現役を引退してしまえば、ウイスキー需要は限りなくゼロになってしまいます。サントリーにとって創業の事業がそんな状況では困るのです。なんとか復活させたい。これまでにもいろいろと手は打ってきましたが、時代の波に抗うことはできなかったのです。消費者の心にこちら側の策がうまく届かず、実に25年もの間ダウントレンドを続けてきたのです」(塚原さん)
かつての黄金期がうそのように、一部の愛飲家にしか飲まれなくなってしまったウイスキー。なぜ消費者の間でウイスキー離れが起こったのか。それを明らかにしてなんとしてもウイスキーのダウントレンドに歯止めをかけたい。創業の事業であるウイスキーの需要を復活させたい。2008年、塚原さんたちはウイスキーの復活を賭け、その原因究明から着手した。
まずは20~30代の男女1,000人ほどを対象に、ウイスキーのイメージ調査(インターネット調査含む)を実施した。すると、つぎのようなネガティブポイントが浮かび上がった。
1.古くさい(おじさんの酒、ウンチクの酒、ギフトで贈りたくない、サラリーマンの上下関係)
2.飲みにくい(アルコール度数が強い、料理に合わない、難しくてとっつきにくい)
3.飲む場がない(周りが飲んでいない、1軒目の飲食店で目にしない、バーには行かない)
これら負の要因は、善きにつけ悪しきにつけ、サラリーマン社会の“濃密さ”が消滅したいまの世相の反映だろう。しかし、これを打開しない限りウイスキーの復権はない。どうすれば若者を惹きつけられるのか。模索の日々が続いた。
が、灯台もと暮らしとはこのことか。サントリーの本社がある台場とは目と鼻の先に、いまでもウイスキーがよく飲まれる酒場があった。東京・銀座の「マルギン」。ある日店をのぞいてみると、そこでは多くのお客さんがウイスキーを飲んでいる。そして飲み方はもっぱらハイボール。昔さながらウイスキーをソーダで割って飲んでいる。しかも老若男女が喜々として口にする。イメージ調査で浮き彫りになったネガティブポイントなどなんのその。そこではウイスキーがつぎつぎに飲まれていた。

ハイボールに馴染みのない世代の塚原さんも飲んでみた。うまい!しかも飲みやすい。
「これだ! これなら古くさいどころか、いまの若者にも"自分たちに合う酒"だと感じられる。ハイボールならウイスキー離れの問題を解決できる。そう確信しました」
塚原さんはマルギンのみならず、ウイスキーがよく飲まれる飲食店をいくつもめぐり、同じようにハイボールが飲まれている光景を目の当たりにして確信を深めっていった。これならウイスキーを復権する秘策にできる、と。
聞いたことはあっても飲んだことがない
2008年秋。さっそく取引先の飲食店に「角ハイボール」を提案して歩いた。古くて新しいウイスキーの飲み方をお客さんに勧めましょう、と。そして狙いどおり、角ハイボールは若い男女の心をとらえていった。その理由はこうだ。
「とりあえずビール、と言ってまずビールから始めますね。でもビールはすぐにお腹にたまってしまい、しかもカロリーも高い。また、よく飲まれていた焼酎にも最近はマンネリ感が漂う。はっきりと顕在化しないまでも、酒に対するこうした不満が若者の間にあったのです。自分たちにフィットしたアルコールがないから、しかたなく低アルコールや甘いお酒を飲んでいた。そこにハイボールが登場したのです。いままでになかった飲み方の酒が若者の嗜好をとらえたわけです」
若者のアルコール離れは、単にアルコールを敬遠するだけでなく、飲みたいと思える種類の酒がなかったことが大きな原因だった。そこに古くて新しい酒=角ハイボールを提案すると、たちまちに若者の間に広がっていった。聞いたことはあっても飲んだことがないハイボール。そんな若者にとってはウイスキーをソーダで割るというだけでも斬新に感じられた。さらに、炭酸で割るためにアルコール度数が低く、口当たりもさっぱりしている。このようにさまざまな要因がからまって、ハイボールは20、30代の若者の心を確かにつかんでいった。
ウイスキー市場全体を牽引した

こうなるとサントリーの角ハイボール展開は一気に加速する。まずは味を統一するために、“正統派の角ハイボールのつくり方”を説いて回った。
正統派の角ハイボールとは…。まず、ジョッキに氷をたっぷり入れ、生レモン果汁を搾る。そこに角瓶のウイスキーをジョッキ3分の1~4分の1ほど入れ、冷えたソーダ水を注いで完成。これが“正統派”だ。
この正統派角ハイボールのつくりかたを飲食店に指導して回り、併せて08年7月に角瓶のハイボール専用サーバー「角ハイタワー」を新たに開発し、各地のフラッグシップ店に導入していった。その結果、08年末には角ハイボールを取り扱う飲食店が1万5000店に達した。
また、一般消費者へ角ハイボールを訴求させるため、同年9月に女優の小雪をイメージキャラクターにCMを全国放映。さらに、ハイボールグラス、角ハイボールジョッキのプレゼントキャンペーンを展開した。
翌09年にはプレゼントキャンペーンのみならず、小売用のハイボール商品として「角ハイボール缶」(350ml)を発売し、飲食店用には「角ハイボール樽詰」を開発して導入を図った。その結果、角ハイボール缶は発売1カ月後に当初計画を1.8倍に上方修正するほどの盛況を示し、また、角ハイボールの取扱い飲食店も09年末には前年比4倍の6万店までに拡大した。まさに角ハイボールが大ブレークした1年となった。
角ハイボールの進撃は10年も続く。球場のスタンドで移動しながら販売するため、背負い型のハイボールサーバー「角ハイおんぶ」を開発し、角ハイボール缶ではロング缶(500ml)を発売。ハイボールを取り扱う飲食店も年末には14万店にまで拡大し(角瓶とトリスのハイボールを扱う飲食店の総計)、角瓶の出荷数量は07年に比べて1.7倍の295万ケースにまで達した。

また、ウイスキーの総需要も09年と10年がそれぞれ前年を大きく上回った。09年は前年比110.3%、10年も前年比116%を記録した。09年は98年(減税による特需の年)以来11年ぶりの前年超え、また10年の2年連続大幅増は27年ぶりという。角ハイボールは角瓶のみならず、ウイスキー市場全体を牽引する大きな役割を担ったのである。
ウイスキーの飲み方のスタンダードをめざす
09年に大ブレークした角ハイボールだが、飲み方のスタイルとして昭和30年代の角ハイボールと大きく異なる点が1つある。飲む器がジョッキであることだ。昔は円柱型や角柱型のグラスだった。グラスの中の角ハイボールにレモンスピリッツを加えて飲んだ。
が、今回はジョッキの角ハイボールに生レモン果汁を搾って飲む。社内でも昔の角ハイボールを知る先輩社員からは「ジョッキで飲むとは邪道」との声もあった。しかし、塚原さんたちには信念があった。ジョッキだからこそいい。ガッツリ飲める感覚。ジョッキにはそれがある。若者にはそれがいい。その信念を最後まで貫き、ハイボールはジョッキというスタイルを定着させた。

11年1月28日、サントリーはハイボール専門店「HIGHBALL BAR新橋1923」を東京・新橋にオープンした。ハイボールをさらに訴求し、ウイスキー需要の拡大を図るためだ。HIGHBALL BARでは角瓶はもちろん、トリス、「山崎」「白州」などのハイボールも提供する。また、HIGHBALL BARは新橋を皮きり全国に展開される予定だ。創業の事業であるウイスキーの復権を賭け、若者の需要を掘り起こした角ハイボール。単なるブームに終わらせることなく、ウイスキーの飲み方のスタンダードをめざし、角ハイボールはその輪を広げていく。
企業データ
- 企業名
- サントリー酒類株式会社
- Webサイト
- 代表者
- 代表取締役社長 相場康則
- 所在地
- 東京都港区台場2-3-3
- Tel
- 0120-139-310
掲載日:2011年3月 2日