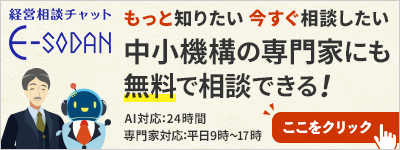あの人気商品はこうして開発された「食品編」
「アヲハタ55ジャム」甘さを抑えたおいしいジャムは作れないか

「ジャム×甘い=おいしい」という食の方程式を再構築—。糖度55度のジャム「アヲハタ55ジャム」が発売された1970年当時、ジャムは糖度65度以上の商品が主流だった。ジャム業界では「甘さ」がおいしさを支配していた。だが、高度経済成長が成熟期に突入し“豊食の時代”を迎えると、消費者嗜好(しこう)に変化が生じてきた。過度の甘さを気にした食生活にスライドし始め、甘さを控える傾向が鮮明になっていった。潮流の変化を敏感に察知したキユーピーは、糖度を抑えてもおいしいジャムは作れないかと開発に着手。ただ、当時は市場に糖度65度以上のジャムしか存在しなく「甘さ」がおいしさの王様だった時代。「ジャム×甘い=おいしい」の方程式を崩すには越えるべき障壁が数多くあった。
お客さまの要望に応えたい
1988年に日本農林規格(JAS)が変わるまで、ジャム類でJASマークを付けることができたのは、糖度65度以上の商品(同年以降40度以上に改訂)。同規格からも分かるように、ジャムでは「甘さ」が大切な要素だった。他社と同じように売れ筋の高糖度ジャムを販売し続け、商品開発リスクを取らない方法もあった。だが、キユーピーは「時代は甘さ離れの傾向にあった。『過度の甘さを控えたい』というのがお客さまの要望。だったら、それに応えたいとの思いがあった」(商品開発本部家庭用開発部加工食品チームの岩松哲哉担当課長)と、低糖度ジャムの開発に着手した経緯を語る。(※低糖度=55度未満-40度以上[日本ジャム工業組合])
もっとも、糖度を下げて「おいしくない」と消費者から評価されては元も子もない。甘さを抑えながら従来のジャムに負けない味の追求が始まった。
甘さとおいしさのバランス発見

開発チームが着目したのが“バランス”だった。甘さを控えることだけを目指すなら、糖度を可能な限り低くすることで対応できる。だが目指したのは、甘さ重視の高糖度ジャムに負けないおいしいジャムだった。
ジャムでおいしさを引き出すには、どうしても一定程度の糖度が必要になる。問題はその程度だ。「フルーツの種類によっては、生のままよりも砂糖などと一緒に煮詰めたほうが、香りが立ちおいしくなる果実がある。どの程度の糖度ならおいしさが軽減しないかの相関関係を探る日々の連続だった」(同)という。試作を繰り返す中で、行き着いた答えが「絶妙なライン」(同)となった糖度55度だった。
もう一つ難題があった。ジャムをゼリー状に固めるには果実に含まれている成分でペクチンと呼ばれるゲル化剤が必要になるが、当時ペクチンの種類には60度以上の糖度でないと固まらない性質のものしかなかった。そのため低糖度ジャムではジャムらしい性状にならず、種々のゲル化剤を検討した結果、当時開発されたばかりの新しいペクチンを採用することでジャムらしい性状を得るに至った。「低糖度でもジャムらしい性状を得るのには相当苦労したと聞いている」(同)という。
信念「7:3の関係」
1970年、種々の課題を克服し国産初となる糖度55度の「アヲハタ55オレンジママレード」は発売された。キユーピーが低糖度ジャムのパイオニアになれたのには、同社に脈々と受け継がれてきたノウハウと経営理念が背景にあった。

キユーピーは1932年にジャム類「オレンジママレード」を発売したジャムの老舗。「フルーツの種類に適した加工技術や、いかに加熱量を減らしフルーツの風味をより引き出せるかなどのノウハウを長年蓄積してきた」(岩松哲哉担当課長)。また、同社には“果実加工は原料を選ぶことによって7割が決まる。残りの3割は創意工夫によって技術を高めること”という信念がある。創意工夫は絶妙な甘さのバランスを発見することや、低糖度ジャムの開発で体現した。
原料となるフルーツでは、1932年にオレンジママレードを発売して以来、ジャムに合った果実の調達ノウハウを積み上げてきた。「どの地域のフルーツをどの時期に収穫するのがベストなのか、昔から培ってきた知恵がある。こだわりの品種がある場合には、世界中を駆け回って探し出す執念と調達網がキユーピーグループにはある」(同)。脈々と受け継がれてきたノウハウと精神がスピード感をもった開発を可能にさせた。
低糖度ジャム、じわり
1970年に満を持して「アヲハタ55オレンジママレード」を投入。しかし、市場の反応は思ったよりも冷ややかだったという。「甘いことがおいしいと思われていた時代、すぐにお客さまから支持をもらえるような状況ではなかった」(岩松哲哉担当課長)。

転機となったのが74年。同時期になると「消費者の摂取カロリーを気にする傾向が強くなり、小売りサイドから低糖度ジャムのラインアップ拡充の声が出てきた」(同)。小売り側の要望もあり、74年にフレーバーに「イチゴ」と、イチゴとりんご、ぶどうを混ぜた「ミックスジャム」を発売。健康志向の高まりに加え、シリーズで販売することで商品棚に置いた際の視認性も向上し「昭和50年前半から売り上げが伸びていった」(同)。
キユーピーによると、同社のジャム類での国内シェアは約30%でトップ。「アヲハタ55ジャム」のブランド単体売上高は公表していないが「キユーピーのジャム類売り上げの80-90%は『55』シリーズ」(同)で、実質的な国内トップブランド商品になった。「ジャム×甘さ=おいしい」という従来の方程式を目標通り「甘さの少ない×ジャム=おいしい」に作り変えることに成功した。
トップブランドの責務

トップブランドだからといって地位に胡坐(あぐら)をかいてブラッシュアップを怠っていては、いつしか消費者は離れていってしまう。
ジャムのおいしさを追求するため、キユーピーは2005年に従来製法では失われていたフルーツの香りをジャムに戻す「おいしさナチュラル製法」を確立。濃縮過程で水分と一緒に蒸発していく香気成分をジャムに還元する製法を開発した。濃縮過程では、さまざまな成分の香りが出てくるが「加熱時においしさに寄与する香りが出てくるタイミングがある。その香気だけを取り出して還元する」(岩松哲哉担当課長)。失われていたフルーツ本来の香りを戻すため「香料を加える必要がない。この製法を取り入れているのはキユーピーだけ」(同)という。
また、13年2月15日には「アヲハタ55ジャム」全10種類を全面リニューアルして発売した。フルーツの糖である「果糖」を新たに加えたことで「食べた瞬間に、フルーツ本来の香りと甘さが“ふわっと”感じられるようになった」(同)。
同時に、ビンのデザインも刷新。ビンの上部を多面体にしてくぼみを付けることで蓋(ふた)を開けやすいように改良した。またロゴの「55」に10種類のフルーツの色彩を入れたほか、蓋の種類も1種類追加し5種類にした。「“少しオシャレなジャム”を買う楽しさをお客さまに提供できれば、また家庭の食卓が少しでも華やかになればと考えた結果」(同)と、笑みを浮かべる。

健康志向の高まりという時代の大きな潮流を先取りし、低糖度ジャムを他社に先駆けて開発したキユーピー。トップブランドになった今では、ジャム市場をけん引していかなくてはならない責務を感じているという。「売り場を奪い合う競争では価格競争に陥り、おいしさを伝える食品メーカー本来の目的がないがしろになってしまう。キユーピーが新商品の開発や商品の改善、ラインアップの拡充、容器の改良などさまざまな取り組みを続けるのは、ヘビーユーザーにさらに親しまれるためだけではなく、まだ食べたことがないお客さまにどうしたら手にとってもらい、口に入れてもらうかを重視しているから。パイの取り合いではなく、パイを広げていくことがトップブランドの責務。そのための試行錯誤をこれからも続けていく」との岩松哲哉担当課長の言葉には、商品開発者スピリッツが宿っている。
企業データ
- 企業名
- キユーピー株式会社
- Webサイト
- 代表者
- 代表取締役社長:三宅峰三郎
- 所在地
- 東京都渋谷区渋谷1-4-13
掲載日:2013年2月27日