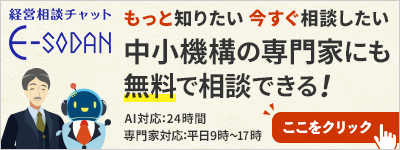あの人気商品はこうして開発された「食品編」
「ゆかり」赤しその漬物をふりかけにして売りたい

赤しそふりかけの代名詞となっている三島食品の「ゆかり」。炊き立ての温かなご飯にふりかけると、赤しそのさわやかな香りが鼻を抜ける。赤しその風味を最大限生かすことに注力した同商品は、具材に赤しそしか使用していない。飾らないシンプルな味つけだけに、素材の良しあしが品質を決める最大のポイントになる。ゆかりの単体売上高は「(業務用家庭用を合わせて)約35億円で推移し、売上高に占める割合は約3割」(重野敦史営業本部企画マネジャー)と、三島食品の屋台骨となった。だが、1970年の発売当初の売り上げは「ないに等しい状態だった」(同)という。浮上のきっかけは、徹底した品質の向上にあった。
根負けした社長
「社長、赤しそを細かく切った漬物が売れています。ぜひわが社でも売らせてください」—。名古屋地域を担当する営業部員のこの提案が、ゆかり発売の発端だった。
1960年代後半、名古屋地域で赤しその漬物が売れ筋となっている情報を営業部員がキャッチ。三島食品は1949年の創業以来、ふりかけ専業の会社だったため、何か新しい商品がほしいと思い「創業者の三島哲男社長(当時)に直談判した」(同)。しかし、返ってきたのは「三島食品はふりかけ屋、漬物は漬物屋が売るものだ」と、一蹴する言葉だった。
社長に否定されたのだから、話は立ち消えたとも思えるが、直談判したのが「非常に熱血漢の営業部員」(同)。おいそれと引き下がるような性格ではなかった。「絶対に売れる」と食い下がり「社長が見る営業日報にしつこいくらい売りたい想いを書き続けた」(同)。最後に根負けしたのは、社長のほうだった。
だが、社長は条件をつけた。「漬物を漬物として売るのではだめだ。わが社には長年積み上げてきた乾燥技術がある。赤しその漬物をふりかけに近づけることができたら、商品化してもいい」と言われた。
ほそぼそと販売開始

社長の指示に従い、開発がスタート。社長から条件はつけられたものの、三島食品には乾燥についてのノウハウがある。赤しその漬物を乾かして商品化することは難なくできると高をくくっていた。
だが、実際に乾燥させてみると、温度が低ければ思うように乾かず、逆に高ければ漬物に含まれる調味料がこげついてしまった。なかなか思うように行かず、当初の目論見は外れた。試行錯誤を重ねた結果「ようやく、それらしい商品ができあがった」(同)という程度で、パッケージも今のように立派な袋ではなく「最初は袋詰めにして、商品名を印刷した二つ折りの紙をホッチキスでとめた程度のもの、その次も透明袋にワッペンを貼った簡素なものでした」(同)。業務用でのほそぼそとした発売だった。
専用工場が稼働
ゆかりが学校給食で少しずつ使用されはじめ、子供の人気メニューとなり次第に広がっていくなど、状況に変化が出てきたのが、一般家庭用としても売り出した1973年ころ。パッケージカラーが赤しそをイメージした紫色のため店頭で目立ったことや、類似商品がほとんどなかったことから、食品スーパー(SM)で取り扱われるようになった。また営業部員が小さなおむすびを作って問屋のセールスや食品スーパーの仕入担当者に試食してもらって味を気にいってもらい、徐々に店頭に置いてもらえるようになってきた。ゆかりをご飯に混ぜおむすびを作って試食してもらう地道な取り組みを行うことで「少しずつ認知度があがっていった」(同)。
味の改良も行った。発売当時は塩辛かったが、1979年には添加食塩を50%減らし、塩辛さを抑えた。このころから徐々に販売量が増加していったという。伸びる需要に対応するため、1988年にはゆかり製造の専用工場が稼働。従来は材料を容器に投入するバッチ式で乾燥させていたが、製造工程を連続ライン化したことで生産効率を向上させた。
品質は妥協しない

1979年、新たな挑戦が始まった。売り上げが伸びるにつれて課題となってきたのが原料の確保。生産農家とともに赤しそ栽培を行ってきたが、在来種では品質に限界があった。そのため、現社長の三島豊氏は赤しその新品種開発を決断した。
新品種を生み出すには、気の遠くなるような作業の繰り返しが必要になる。まず、従来種の中から有望な株を選び栽培する。その中から香りや色にバラつきがなく安定した品質を備えた株を再度選び出し、栽培するという作業をバラつきがなくなるまで繰り返す。 99年、ついに香りと色、風味を固定化した新品種が完成した。気がつけば、約20年の年月が過ぎていた。品名は豊かな香りという意味で「豊香」。00年に農林水産省から新品種として登録された。苦労が報われた瞬間だった。
品質へのこだわりは品種だけではない。77年から導入した全量買い取りの契約生産制度では、契約農家に赤しその自家採種を禁止、異品種の混入を防いでいる。また、香りと色合いが最も優れているとされる株上部の新芽だけを商品に使い、他の部分は「堆肥(たいひ)として使用する」(同)という徹底ぶりだ。
動きだした三島食品

ゆかりは発売から42年が経つが、紫と緑のストライプを基本としたパッケージデザインに変更はなく、また製造工程も大きく変えていない。重野敦史営業本部企画マネジャーは「お客さまは、ゆかりといえば紫色のパッケージを思い浮かべ、そこに安心感を抱いていただいている。不用意に変えることはできない。また、品質を高めるための改善はするが、単に短時間化、省人化のための工程変更をするつもりはない」と述べ、確固としたスタンスを見せる。
もっとも、変化を嫌い硬直化しているわけではない。2010年ころから、黒のりにゆかりの成分を混ぜた味付けのりや、ゆかりのふりかけを飴に入れたものなど、他社との商品コラボレーションを展開。また今は、七草粥のシーズンに合わせて、冷凍食品会社のテーブルマークと電子レンジで温める同社製トレー入り白かゆに、ゆかりをトッピングとして使用する提案を小売業に共同で行っている。「以前は、自社だけで商品をどう売るかしか考えていなかった。他社との連携は、主導権が自社になくなってしまうマイナスイメージばかりがあったため、二の足を踏む時代が長く続いていた」(同)と振り返る。

しかし、食品メーカーとして目指すところは、消費者に支持され必要とされること。「新しいチャレンジをしなければ、ゴールは遠くなる」(同)との判断から、他社との商品コラボや共同提案にも踏み切った。実際に他社と連携してみると「コミュニケーションを密に取り、しっかり信頼関係を築けば、問題ない」(同)ことを知った。「よく小売業様から三島食品は『地味な会社。宣伝ベタな会社』と言われていた。だが、商品コラボなどの新しい活動をするようになり『三島も動きだした』と言われるようになった」(同)と笑みをこぼした。
※「ゆかり」は三島食品株式会社の登録商標です。
企業データ
- 企業名
- 三島食品株式会社
- Webサイト
- 代表者
- 代表取締役社長:三島豊
- 所在地
- 広島本社:広島市中区南吉島2-1-53
東京本社:東京都杉並区浜田山4-10-25
掲載日:2012年12月27日