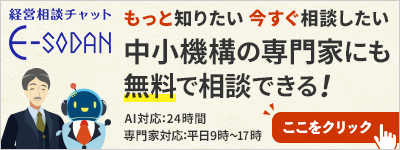あの人気商品はこうして開発された「食品編」
「焼肉のたれ」・「黄金の味」なんとか家庭に焼き肉を持ち込めないか

エバラ食品工業のロングセラー商品「焼肉のたれ」は高度成長期の1960年代後半に開発・発売された。人気落語家月の家円鏡(現・橘家圓蔵)によるテレビCM効果も手伝って一躍ヒット商品となった。ホットプレートの家庭への普及と軌を一にしている。その後発売された「黄金の味」も、日本の牛肉消費を拡大させるうえで一役かった。エバラといえば「焼肉のたれ」といわれるように、この基幹商品がいまもなお同社の屋台骨を支えている。
焼き肉店繁盛の要因はタレにある
牛肉や豚肉にタレを漬け込んで焼くという焼き肉スタイルを家庭に広く普及、浸透させた食品メーカーはどこだろう。そう、エバラ食品である。
エバラ食品が他社に先駆けて「焼肉のたれ」を開発、発売したのは1968(昭和43)年のことだった。
戦後の食糧難時代を脱して高度成長期に入ると、消費者のタンパク源も大豆や魚に代わって肉の比重が増しつつあった。首都圏随所で焼き肉店が繁盛し始めており、それに目をつけたエバラ食品の創業者で当時の社長の森村國夫氏が「この焼き肉をなんとか家庭の食卓に持ち込めないか」と発想したのが「焼肉のたれ」の開発の発端だった。

さっそく行動を開始した森村氏は、数人の部下を引き連れて都内や横浜周辺の焼き肉店の食べ歩き調査を開始する。とりわけ大衆的な繁盛店を選んで食べ歩いたが、どの店でも元気盛りの若者が文字どおりガツガツと食べている。たっぷりタレを漬け込んだ肉を焼くにおいがことさら食欲をそそる。
焼き肉店繁盛の要因は、まさに肉を漬け込むタレにある—そう読み解いた森村氏は、いくつかの焼き肉店の店主にタレの作り方を聞いてみたが、タレこそは店のノウハウが凝縮された秘伝中の秘伝。やすやすと教えてくれるはずもない。
独自にタレの開発に挑んだものの、なかなかいい味が出ない。試行錯誤が続くが、森村氏には幸い、ウスターソースをつくった経験があった。その経験を活かし、しょう油をベースとして開発に取り組む。
今も受け継がれる「発見」の眼
当時はまだ、食肉流通にも現在のような冷凍・冷蔵システムが完備していない。このため肉の鮮度にもいささか問題があり、臭みが強かった。どの家庭でも手軽に買い求めることができるような安価な肉でも美味しく食べられるタレはつくれないか—。そこに開発の熱情が最大限注ぎ込まれた。当時の商品開発について、家庭用商品開発課担当課長の清水憲一さんはこう説明する。
しょう油をベースに、ニンニク、ショウガ、タマネギなどの香味野菜やブラックペッパー、レッドペッパーなどの香辛料をブレンドし、古い肉に残りがちな獣臭をマスキングするためゴマ油を用いました。酒やもろみ、あるいは乳酸、コハク酸、有機酸などの旨味成分も加えました。これらの成分の絶妙なバランスに到達するまでには、数限りない試作品をつくり、そしてようやく完成品にこぎつけたわけです。」
焼き肉人気の秘密はタレにあると読み解いたことを、同社では「発見」と称している。この「発見」こそが商品開発の要諦だとし、いまでもあらゆる商品開発の最重要ポイントに「発見」を置いている。
商品開発のヒントは市場のどこにでも転がっているが、濁った眼にはそれは見えない。同社が重きを置く「発見」は、市場からヒントを鋭敏に読み取る眼識にある。商品開発の担当者は、つねに鋭敏な「発見」の眼を養っておかなければならない。同社の商品開発の要諦である「発見」は、まさにその原点がこの「焼肉のたれ」にあった。

同社が「焼肉のたれ」を出す以前の日本の肉料理は、スキヤキやカレーなど鍋で煮込むものが多く、肉を家庭で焼いて食べるという食習慣は少なかった。その食習慣にどうやって一大変化を起こさせるか。「焼肉のたれ」の開発には、食文化への挑戦の意欲も込められていた。
しかし、販売はあたかも瀬踏みをするような慎重さで始められた。横浜市鶴見区の精肉店での小規模な限定販売。精肉店店頭のショーケースの上段に商品を並べてもらった。売れるという確信はあったものの、当時はまだ大量生産の設備が整っておらず、大々的に売るには商品供給力に難があった。それに、せっかくの自信作を開発しても、供給力を整えて市場で優位に立つ前に、大手メーカーから類似商品で攻撃を仕掛けられるようなことがあっては元も子もない。息を潜めるような、地域限定の静かなスタートだったが、これを同社では「もぐら作戦」と称している。
あたかも土中に潜ったようなこの「もぐら作戦」は奏功、想定を上まわる上々の出足だった。赤を基調としたパッケージデザインも、肉しか置いていない殺風景な精肉店のショーケースの上でよく目立った。焼き肉が家庭で美味しく食べられると知った主婦が相次いで買っていく。「焼肉のたれ」が食肉自体の売り上げも押し上げたため、店主にも喜んでもらえた。
関西でも受け入れられる味を

こうして市場の手応えを得た同社は、翌69年、一部のスーパーでも販売を開始する。次いで70年には6カ月間、静岡県でテレビCMを流して本格的なテストマーケティングを実施。その高評価を踏まえ、関東から中部、東北、そして中国、関西、九州へと漸次販売エリアを拡大していった。
72年には横浜市神奈川区松見町にあった本社工場が手狭になったため神奈川県伊勢原市に移転。それまでガスによる直火でおこなっていた加熱・殺菌工程を伊勢原工場では蒸気加熱方式に改めたが、その結果、熱効率が向上し、歩留まりが格段に良くなり、商品供給力も上がった。
70年代に入ると、市場にも徐々に変化が起き始めていた。高度成長を経て、消費者は量的な満腹感を求めるよりも、より美味しいものを求めるニーズを強めつつあった。そうした消費者ニーズの変化に対応して開発したのが、「黄金の味」である。清水さんは語る。
「このころになると、商品開発にコンセプトという言葉が使われるようになりました。『黄金の味』を開発するにあたっては、“高級感があって関西でも受け入れられる味”というわけです。しょう油ベースの『焼肉のたれ』を最初に関西に持ち込んだとき、味の嗜好性の違いに苦戦したので、その反省に立った開発です。『焼肉のたれ』はしょう油味を好む東日本をターゲットに開発した商品だったので、どうしても甘めの味を好む西日本向きではなかったんですね。」

「黄金の味」にも、もちろんしょう油や、砂糖などは使っているが、決定的に違うのはフルーツをベースにしているところだ。そのうえに畜肉系ブイヨンやエキスなども加え、味に厚みをつけた。フルーツはリンゴ、モモ、ウメなどで、それらが30%以上も入っているので、飽きのこないさっぱりとした甘さのたれに仕上がった。
肉をタレに漬け込んでから焼くというのが「焼肉のたれ」だったが、「黄金の味」は素焼きにした肉をタレにつけて食べて美味しいと感じられるように商品設計している。当時開発に携わった担当者は「飲めるくらいのタレの味にしなければならない」という意気込みで開発したという。
どういうブランドネームにすれば高級感をもたせたることができるか、これにも一苦心あった。「エバラ焼肉のたれ ゴールド」「エバラ焼肉のたれ デラックス」等々の候補があがったが、森村氏の胸にはいまひとつ響かない。最終的に森村氏の鶴の一声で、当時人気番組だったNHKの大河ドラマ「黄金の日々」にヒントを得た「黄金の味」に落ち着いた。重量感のあるこのブランドネームは消費者に好感をもって受け入れられ、またたくまに全国に浸透した。

2012年3月期決算におけるグループ全体の売上高は約490億円で、うち食品事業のそれが約438億円。食品事業のうち家庭用は79.6%、そして家庭用のうち肉まわり調味料はその半分強を占めている。
すでに家庭用の焼き肉のタレは6ブランド、26品目に拡大したが、同社の経営を飛躍させた「焼肉のたれ」、そして経営基盤の安定化に大きな役割を果たした「黄金の味」は今なおロングセラー商品として同社の経営を盤石に支えている。
企業データ
- 企業名
- エバラ食品工業株式会社
- Webサイト
- 代表者
- 代表取締役社長 宮崎遵
- 所在地
- 横浜市西区北幸2丁目5番15号 日総第3ビル
掲載日:2012年6月15日