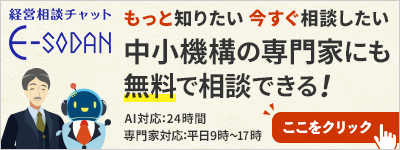あの人気商品はこうして開発された「食品編」
「いちごみるく」これまでにないキャンディ、“噛む飴”を開発する

サクマ製菓のクランチキャンディ「いちごみるく」は、発売後40年超の歳月を経てなお進化を遂げ、新たな世代の需要層をとらえて安定成長を持続している。2011年の東日本大震災後は、ロングセラー商品の強みともいうべき商品の信頼感から大きく売上げを伸ばした。キャンディの需要層にも否応なく世代交代が進む。そのため、同社では新たな需要層の発掘に向けた商品開発が進んでいる。
チョコをアソートしたキャンディが大ヒット

1970年8月、サクマ製菓がわが国最初のクランチキャンディ「いちごみるく」を発売した。薄い飴の中に「いちご」と「ミルク」の2種のフレーバーが多層状に挟み込まれた画期的なキャンディだったが、実はこの開発史にはそれに先立つ商品が存在していた。チョコレートキャンディ「チャオ」だ。
チョコレートキャンディ「チャオ」は、飴の中にチョコレートを包み込んだ商品だ。飴の中に飴以外の素材を挿入した商品が市場に存在しなかったうえ、挿入した素材が当時はまだ貴重品のチョコレートだったことから爆発的にヒットした。まさしく「チャオ」は一世を風靡した商品として日本のキャンディ史を彩っている。
「チャオ」の開発、それは商品企画部課長の松田文貴さん(30代)にとってはもちろん生まれる前の出来事だが、「当社の商品開発には当時から先駆的なところがあり、それが『チャオ』に次ぐヒット商品『いちごみるく』の開発にもつながっていきます」と自社の開発精神を分析する。
1968年、「チャオ」の大ヒットで勢いづき、当時の山田隆重社長から製造現場の職人(社員)に下命が発せられた。
「洋菓子のミルフィーユのように薄い飴の層を幾層も重ね、その層に異なるフレーバーを付けたキャンディができないか」

前代未聞のキャンディであり、その命を受けて現場の試行錯誤が始まった。
しかも、このとき社長が現場に要求したのは飴の多層化だけではなかった。「噛む飴」という新しいコンセプトを求めてきた。当時の日本の飴には、長時間なめ続けることでフレーバーを味わう硬い飴しかなかった。が、そこにフレーバーのみならず、噛み砕いてサクサクとした食感も楽しめる飴=キャンディを投じようというのだ。新たな需要を喚起せんという社長の目論見だった。さらには、従来の硬い飴より噛み砕けるキャンディのほうが早く食べ終えるので連食性が高まり、それにより市場の拡大が期待できる。そんな読みも社長の胸中にはあった。
噛み砕けるキャンディが誕生した
製造現場が噛む飴の製品化にこぎつけるまでにほぼ2年の歳月を要した。選択したフレーバーは「いちご」と「ミルク」。その背景について松田さんは語る。
「いちごは子どもたちが大好きなフレーバーです。また、当時牛乳は貴重な栄養源として高く評価されていました。ならばこれを合体させて『いちごみるく』でいこう。こうしてフレーバーの方向性が決まったのです」
いちご味とミルク味をブレンドして1つの味にしてしまうのではおもしろくない。それぞれを層状に重ねたキャンディに仕上げてこそ、新しい商品価値を訴求できる。が、それには製造工程に大きな困難が立ちはだかっていた。
当時の飴づくりはすべて職人の手作業。砂糖と水飴をコトコト煮詰めてつくった複数の種類の飴を、職人が2人がかりで層状に重ねていく。ところが飴は熱せられた状態だとドロドロの液体で流動性がありすぎる。その反対に冷えすぎると固まってしまい思うように伸びてくれない。流動性がありすぎず、しかし固まってしまわないちょうどよい温度帯を探りあてるまでに、なんども試作を繰り返したという。
そんな製造現場の苦労を経て、層状で噛み砕ける日本初のキャンディが誕生した。この三角形のキャンディはひねり包装で個別に包まれている。ひねり包装とは、包材の両端をひねって中身を包む方法であり、同社の消費者調査ではひねり包装だと食べる際に両端を軽く引っ張るだけなので容易と支持が多かった。
キャンディの包装が決まると、つぎはパッケージのデザインだったが、これが黄色とピンク色のサイケデリック模様という斬新なデザインのため市場をあっと驚かせた。

考案したのは同社でアルバイトをしていた東京芸大の美学生(河北秀也・東京芸術大学教授)。当時、こんな派手なパッケージデザインの食品はなかった。そのため営業の現場からは「とんでもない。こんなデザインの菓子は売れるはずがない」と猛烈な反対が起こった。
しかし、社長には事業家としての新商品に対する強い確信があった。「新しい酒は新しい革袋に盛れ」の格言があるように、斬新な商品は斬新なパッケージでなければならない。そう考えて営業現場の反対を退け、サイケデリック調のデザインで押し切った。そして、この社長の勘はまんまと的中した。斬新なデザインが若い女性や子どもたちの目を奪い、商品の認知をまたたく間に広げていった。
時代に応じたリニューアル
73年2月、第18回全国菓子博覧会で「いちごみるく」が高松宮名誉総裁賞を受賞。そして同年にはレモン味でさっぱり感を演出した姉妹品「れもんこりっと」を発売し、さらにクランチキャンディの支持層を広げていった。
そして順調に売上げを拡大した70年代半ば、「いちごみるく」は売れ筋商品としてキャンディ市場で確固たる地位を築いた。
発売から約10年間、飴の生地は現場が四苦八苦しながらもていねいに手作業で練っていたが、需要が大きく伸長したために手作業では対応しきれず、機械を導入することになった。
「飴はヨーロッパ渡来の食文化のためか、飴の生産用機械は外国製のものが多く、いまでもヨーロッパ製がリードしています。当社では、チョコレートキャンディ『チャオ』の生産機械はイタリアから導入しました。また、『いちごみるく』もバッチ生産に限って職人の手作業で対応していましたが、生産量が増え、さすがにそれでは対応しきれなくなったため、ドイツから機械を導入したわけです」(松田さん)

この量産設備の導入もあいまって、80年代はさらに好調に売上げを伸ばした。が、その後の市場ではバブル経済の崩壊と軌を一にするように消費者意識が変化し、低カロリーやカロリーオフがもてはやされるようになる。「いちごみるく」が高カロリー商品というわけではなくても、その甘さを敬遠する消費者がしだいに増え、90年代はそれまでの伸びが鈍化し、2000年のピークを境に需要はダウントレンドに入ってしまった。
同社でもこの市場の変化に対応した新たな模索が始まる。が、なかなか妙策は生まれない。苦闘の日々を経てようやく再浮上のきっかけをつかんだのは、09年の全面リニューアルだった。「いちごみるく」の糖分を低く抑えながらも、いちご味のおいしさを一段向上させるため、福岡県の「あまおう」のいちご果汁(100%)に切り替えた。
ブランド力・信用力を次代へつなげる
このリニューアルによって再び消費者の嗜好をとらえ、売上げも上昇軌道を回復する。配合の改良によりキレ味をよくしたことで連食性が上がり、需要の拡大につながった。
食品スーパーや総合スーパーでの売上げが7-8割を占めるが、このリニューアルを機にローソンやサークルKなどのコンビニにも販路が拡大。特にコンビニでは、冷感の糖衣をコーティングした夏限定商品「冷たいいちごみるく」、チョコをコーティングした冬限定商品「チョコいちごみるく」など季節限定の商品戦略も奏功しているという。
「『いちごみるく』の核となる需要層は40-50代で、『いちごみるく』を食べて育った世代です。それはまさしく商品のブランド力、信用力を表しているのですが、その強みを守るだけといいますか、それに安住していては先細りになってしまいます。『お母さんが子どもに食べさせるキャンディ』がこの商品の原点ですので、これからも20、30代のお母さんにも食べていただき、子どもさんに食べさせていただけるように工夫することが大切なことです」(松田さん)
40年以上前、日本初のクランチキャンディとして開発され、当時の子どもたちを魅了した『いちごみるく』。ロングセラーを経て中核購買層の年齢も上がっているが、次代を担う子どもたちへの訴求に向けたさらなる挑戦は続けられる。
企業データ
- 企業名
- サクマ製菓株式会社
- Webサイト
- 代表者
- 代表取締役 山田隆男
- 所在地
- 東京都目黒区中央町1-5-2
掲載日:2012年5月 9日