Be a Great Small
協同組合だからこそ乗り越えた!カーボンニュートラルに立ち向かう省エネ改善「協同組合ウイングバレイ」
2025年 5月 1日

日本の自動車産業は100年に1度という大変革期を迎えており、サプライヤーにもその波は襲いかかっている。協同組合ウイングバレイへのハンズオン支援も、「省エネ改善」という複雑で根気のいる取り組みに、当初は参加企業全員が難色を示す厳しい課題だった。それでも完遂できたのは、取り組みの必要性を理解させるアドバイザー(AD)の説得力と、参加企業の「他社に後れをとりたくない」という協同組合ならではの相互研鑽する体質が奏功した結果である。
「からくり改善」から始まったハンズオン支援
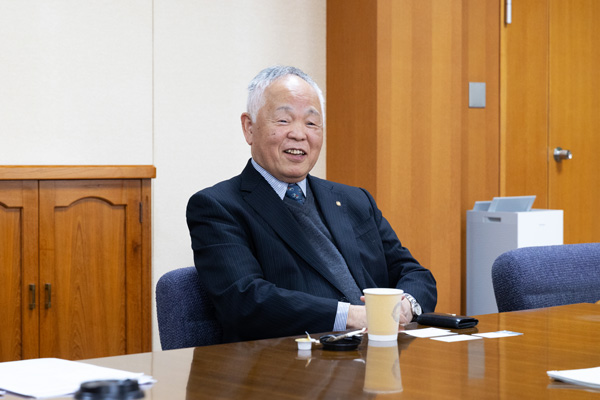
協同組合ウイングバレイは、1962年に大手自動車会社のサプライヤーが集まり設立され、後に岡山県総社市の工業団地に主要拠点を移した。現在の組合員数は12社。機械加工、プレス加工、溶接組み立て、金型製造等、自動車をはじめ様々な部品の生産に関わっている。
その歴史は、主要取引先の変遷に翻弄され続けた歴史でもある。自動車産業が右肩上がりで成長していた時代は、ピラミッド型事業構造の中で共存共栄の関係を築いてきた。しかし、2000年代に業界構造が激変する中、その関係も様変わりしはじめた。「今までの仕事のやり方では立ち行かなくなる」。組合員企業にも危機感が広がり、生き残りには他社からの受注を拡大することが不可欠となった。
そうした中で出会ったのが、中小機構だった。2015年に中小機構が工場の生産性改善で協力することになった。ただ、晝田眞三ウイングバレイ理事長(ヒルタ工業株式会社会長)は「中小機構のことは、工業団地移転時の高度化資金融資の提供者というイメージで見ていた。だから最初は自動車産業の指導が本当にできるのかという思いがあった」と当時を振り返る。しかし、中小機構から最初に提案されたのは「からくり改善」だったことから、見る目が変わった。からくり改善は、大きな投資をせずに、現場の創意工夫で作業効率の改善や課題を解決するもので「これなら資金がなくても各社が無理なく参加できる」と思えた。もともと新入社員研修や管理職研修を共同で行なっており、協力して取り組むことには慣れていた。からくり改善はその後、晝田理事長が会長を務める岡山県中小企業団体中央会と連携するかたちで、4年間にわたって実施された。その後、中小機構の支援は、2017年より「からくり改善」から「製造現場の改善」、「自主保全」と取り組む内容を変えて現在に至っている。
晝田理事長は「同じ自動車部品の企業だが、得意分野はそれぞれ別で、他社にノウハウが漏れるのを恐れる必要はなかった。だから、みんなで各社の工場を見ては改善点を指摘しあえる関係ができた。同時に『あの会社ができていて、なぜうちができていないのか』という競争心があったのもよかった」と、協力と競争がいい具合に作用したと指摘する。
全会一致で決まった省エネ改善への取組み

長期にわたったハンズオン支援も最終段階を迎え、2023年9月から「省エネ改善」に取り組むことが決まった。折しもカーボンニュートラルへの対応が待ったなしの状況となり、大企業各社は自社が排出する温室効果ガスだけでなく、サプライチェーン全体にも取り組む必要に迫られていた。
組合員企業もそうした状況は把握しており、取引先から排出量の状況を報告するようにと要請されている段階だった。「いずれは、自社でも排出削減に取り組まなければならない。でもどうすればいいのか」。同時期に世界のエネルギーコストが高騰する事態も発生するなど、各社は差し迫った課題に直面していた。こうした背景から、ハンズオン支援の総仕上げとして全会一致で省エネに取り組むことが決まり、参加企業も過去を上回る社数となった。
田村寛人ウイングバレイ事務局長は、最終支援を前に心に期していることがあった。
「今回は、将来を担う次世代リーダーにはこだわらず、むしろ組織全体を動かせる人材をプロジェクトメンバーに選出したい」と、中小機構側の取りまとめ役である油木正幸中国本部シニアADへ申し出があった。これは、必ず成果を出して、何としても自社内に活動を浸透・定着させたいというカーボンニュートラル対応への強い思いからであった。
大荒れの様相を呈したキックオフ会

省エネ改善のアドバイザーとして中小機構が派遣したのが、青戸一義AD。青戸ADは大手家電メーカー協力企業の勤務時代に、自社工場の省エネと生産性改善をはかり、経営改善を実現させた経験のある省エネのスペシャリストであった。青戸ADはプロジェクトメンバーが集まった初回ミーティングでいきなり「次回までに各自自社工場の使用機器リストを作成し、それぞれの電力使用量を測定してください。工場の配線図も用意してください」と事もなげに告げた。それを聞いた参加メンバーからは「何百台もある設備1台ごと、電球1本ごとまでなんてできるわけがない」と青戸ADに食ってかかる者が現れるなど、会は大荒れの様相を呈した。
実際、参加者が会社に戻って、工場の各部門の班長に青戸ADの指示を伝えても「この忙しい時にそんなことできるわけない。一体どれだけの時間がかかると思っているのか」と取り合わない反応が大半だった。長かったコロナ禍が明け、自動車業界は挽回生産の真っ最中で工場は多忙を極めていた。
横並びの競争意識が推進の起爆剤に
そもそも、各社はこれまでも省エネには取り組んできた自負があった。そのため今回の省エネ改善についても、やり方さえ教えてくれれば自社でやれると思っていた。ところが、青戸ADが与えた宿題は各社の予想のはるか上をいく容赦のないものだった。田村事務局長は、各社から送られてくる批判や苦情のメールを見て先行きの困難さに頭を抱えた。参加企業の中には、ウイングバレイの理事会社も4社含まれていた。理事会社の社長は現場から上げられる「無理だ」という声を聞きながらも、「うちらはやらないといけない」と腹をくくった。
一方、青戸ADは提案した改善プロセスに揺るぎはなかったが、各社がやや苦しんでいる空気を察し、「全工場を対象とせず、モデル工場を設定し、そこから始めてはどうか」というアドバイスを行い、使用機器リスト作成と消費電力量の測定作業が始まった。「あそこの会社が始めたようだ」という話が他社に伝わると、無理だと思い込んでいた者も重い腰を上げて対応を始めた。結局3回目のミーティングの時点で、全社が作業を完了させた。中には休日出勤をして測定する者もいたが、とにかくやり終えた。最初は無理だと言いながらも一度やると決めたら、しっかりと対応する。これが、自動車サプライヤーとしての自力なのだろう。
“見える化”が全員を動かした
省エネ改善の本番はここからだった。リスト化とエネルギー測定で、工場のどの部分で電力が大量に消費されているのかが見える化できた。そこから対策を立てる方針を明確に決めることができた。この時点で青戸ADがなぜ設備1台ごとにリスト化が必要と語ったのか、真の意味をメンバーは理解することができた。ある企業では、照明が意外にも大きな電力を消費していることが分かった。朝一番に出社した社員が工場全ての照明を付けていた。「とにかく電気を切れ」という指示が即座に出せた。具体的なデータがあるから、説得力も増す。照明のLED化は思いついても、電気を消すという家庭なら当たり前のことに気づいていなかったのだ。お金をかけなくても省エネができることが実証された。
また、工場の設備に供給する高圧エア用コンプレッサーの電力消費が大きいことも分かり、取り組んだのが設備や配管からのエア漏れ対策だった。そこで、エア漏れ音の大きさで5段階に分類し、それを電気代に換算することにした。現場の社員にもその数値を示し、エア漏れがいかに金のムダなのかを説明し、対策を促した。
設備にバルブのコックを設置し、稼働していない時にはエアの供給を止めるという対策も講じた。また、抜本的な対策として、コンプレッサーを省エネタイプに置き換える企業も現れた。しかし、これには投資が伴う。ここでも、電力使用状況のリストが役立った。経営者に「この投資をすれば、電気代がこれだけ削減でき、何年で投資を回収することができる」という資料を示し、稟議を無事通すことに成功した。
活動を浸透・定着させるための人財と仕組みづくり

各社それぞれが対応に取り組んだ成果は、プロジェクト会議で次々と報告された。メンバーは相互に各社工場にも行き来し、導入成果を自分の目で確認したり、新たな課題を指摘したりと、隠すことなく見せ合った。ある会社が油圧ユニットにインバータ制御を導入したら、それを別の社が真似るなど、成果は互いに共有されていった。ある社は小さな取組みを積み重ねることで年間の電力代を136万円削減、また別の社はコンプレッサーの更新で年間約1,000万円もの削減を実現させた。
プロジェクトに参加した新興工業株式会社技術部の北尾晃一氏は「最初はなんでこんな大変なことをと思ったが、やってみると毎月の電力使用量が目に見えて落ちていくという感覚が面白かった。会社がこちらの提案を見て大きな設備投資をする判断をしてくれたので、これからさらに減っていきます」と成果に満足している。株式会社共立精機生産技術グループの名畑賢和氏は「測定をすることで、毎月の莫大な電気代を知り衝撃を受けた。なるほどこれはやらないといけないと思うようになった」と最初の見える化が取り組むモチベーションになったと語る。ヒルタ工業株式会社第一生産本部の竹内俊二氏は「実は最初は上司に『無理です』と言いました。実際工場はとても忙しかったのです。でも周囲も理解して協力してくれるようになったので、やり遂げることができた。他社の工場を見ることがとても参考になった」と振り返る。
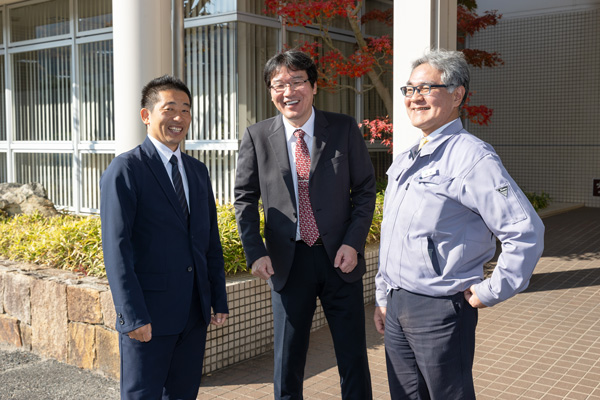
一連の最終的な成果は、プロジェクトメンバー、上司はもとより、組合に参画している企業全ての社長の前で報告された。自社のプロジェクトメンバーが大勢の前で堂々と発表する姿に、「うちも他社もこんな大きな成果がでたのか」、「うちの社員がこんなに立派になったのか」と社長を驚かす場面もあった。田村事務局長が願った「必ず成果を出し、自社内に活動を浸透・定着させるための人財と仕組み」がしっかりと達成されていた。
企業データ
- 企業名
- 協同組合ウイングバレイ
- Webサイト
- 設立
- 1962年11月
- 会員数
- 12社
- 代表者
- 晝田眞三 氏
- 所在地
- 岡山県総社市久代1408番地の6


